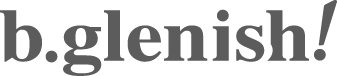「美肌」「体が整う」キレイになる!決定版 “ぬか漬けライフ” 入門

江戸時代から続く日本の食文化「ぬか漬け」。腸活はもはや日常となった昨今、「ぬか床のある暮らし」も注目の一途です。漬けてみればみるほど、栄養価を知れば知るほど、ぬか漬けが体の中からキレイになるための日本人の知恵そのものであることがわかります。改めて、その驚くべき美容・健康効果とともに、自宅で漬けると直面するさまざまな疑問もピックアップ!決定版“ぬか漬けライフ” 入門をお届けします。
目次
・そもそも「ぬか」とは?
・ぬか漬けは乳酸菌を生かした代表レシピ
・注目の免疫ビタミン「LPS」
・美容面でも注目の「LPS」
・複雑な成分も米ぬかの「チカラの源」
・ぬか床はぜひ無農薬の米ぬかで
・自宅でぬかを漬けると直面する「どうすればいいの?」Q&A
・“ぬか漬けライフ”でキレイに!
そもそも「ぬか」とは?
ぬかは穀物を精白したときにできる、果皮、種皮、胚芽などの混合物のこと。お米の場合は玄米を精米するときに出る粉がぬか(米ぬか)です。玄米10kgでだいたい1kgがぬかになります。この約1割の中にお米の栄養素の9割が含まれているといわれています。美味しくても白米はほとんどが炭水化物です。
【ぬかに含まれる主な栄養素】
大さじ1杯の米ぬかには玄米茶碗2杯分もの栄養素が!
・食物繊維・・・・・整腸作用、血糖値上昇の抑制、血中コレステロールを下げる。
・マグネシウム・・・骨や歯の形成、筋肉の収縮・弛緩を促し、酵素を活性化する。
・鉄・・・・・・・・全身に酸素を送る役割。不足すると貧血やめまいを引き起こす。
・ビタミンB1・・・・糖質をエネルギーに変える。疲労回復、皮膚や粘膜の健康維持、神経機能を保つ。
・ナイアシン・・・・疲労回復、血行促進、皮膚や粘膜の健康を保つ。コレステロール値を改善。アルコール分解を助ける。
・ビタミンE・・・・ 抗酸化作用、血圧低下、悪玉コレステロールの減少させる。
・カリウム・・・・・血圧を下げる。余分なナトリウムを排泄する。
ぬか漬けは乳酸菌を生かした代表レシピ

栄養の宝庫で捨ててしまうにはあまりにももったいない米ぬか。その米ぬかに塩と水を混ぜ合わせた「ぬか床」に野菜を漬けたものがぬか漬けです。原理はとてもシンプル。いわゆる乳酸菌発酵です。腸内で悪玉菌の繁殖を抑え、腸の働きをサポートする乳酸菌が豊富なぬか漬けは「腸活」にぴったりの食べ物です。 乳酸菌はあらゆるところに存在する常在菌。米ぬかにも野菜にもぬか床をかき混ぜる私たちの手にもいます。ぬか床の中ではこの乳酸菌や酵母菌が野菜の糖類やビタミンを栄養に増殖。発酵が促され、酸味、風味、旨味を引き出すとともに、米ぬかに含まれるビタミンやミネラルが野菜に浸透し栄養価が高められていきます。例えばきゅうり。1本100gのきゅうりは、生だとカリウムは200mg、ビタミンB1 は0.03mg。ぬか漬けにするとカリウム610mg(約3倍)、ビタミンB1 0.26mg(約8.7倍)になります。※日本食品標準成分表2020年版(八訂)より
注目の免疫ビタミン「LPS」
ところで「LPS」という物質をご存知でしょうか。正式名称は「リポポリサッカライド」。体の免疫システムを活性化する働きがある注目の物質です。主に土の中や海の微生物に存在するため、野菜(特に根菜類)や穀物、海藻類などに含まれ、米ぬかにも大量のLPSが含まれています。
LPSが免疫に作用するメカニズムについても触れておきましょう。私たちの体は細菌やウイルスなどの異物が侵入すると、排除するためにマクロファージという免疫細胞が仕事をします。このマクロファージの活性に役立つのがLPS。活性化したマクロファージは、侵入した細菌やウイルスによる感染拡大を防ぎます。感染した場合でも回復が早まる効果が期待でき、アルツハイマーの予防や花粉症、がんの予防にも効果が期待されています。
美容面でも注目の「LPS」
LPSは肌の免疫機能にも作用します。LPSによって活性化されたマクロファージは、肌に侵入した病原菌やウイルスなどの異物を排除する能力が高まるため、肌トラブルを防ぐことができます。線維芽細胞の増殖を促進する物質を分泌し、ヒアルロン酸やエラスチンの生成を促す報告があるようです。
LPSはマクロファージだけでなく、表皮細胞(ケラチノサイト)など、直接肌の細胞にも作用し美肌へと導くと考えられています。たとえばターンオーバーの促進。LPSが表皮細胞を刺激すると一酸化窒素が作られ、ケラチノサイトの移動=肌のターンオーバーが促進されるといわれています。毛乳頭細胞を活性化させ、発毛や育毛に良い影響を与えることも示唆されています。
複雑な成分も米ぬかの「チカラの源」

米ぬかはほかにフィチン酸、フェルラ酸、γ-オリザノールなど多くの成分を含んでいます。お米の一番健康に良いところを削り取ったものとしかいいようがありません。美容面では色素沈着の改善やエイジングの肌悩みを改善させる効果が期待できるフィチン酸、優れた抗酸化作用やメラニン生成の抑制に働くとされるγ-オリザノールのエビデンスに期待が寄せられています。
ぬか床はぜひ無農薬の米ぬかで
米ぬかは1kgあれば付け合わせとなる程度のぬか漬けを毎日作り続けられます(家族の人数が多い場合は2〜3kg)。あとは、カップ1杯程度の足しぬかをしていくだけですので、大量に必要なものではありません。
少し価格は高くなりますが、ぬか床には自然栽培や自然農法で育った国産米から生み出されたぬかをおすすめします。もちろん、「食品衛生法」によりどのメーカーのぬかも安全性は保障されているため過敏になる必要はありませんが、お米の残留農薬はぬかになる胚芽や果皮・種皮に溜まりやすいとされています。近年は農薬などによって細菌が取り除かれ、食事から取り入れられるLPSは低下しているといわれています。無添加のぬか床で、時間をかけてたっぷりの乳酸菌を育てていくと愛着も湧くはず。
自宅でぬかを漬けると直面する「どうすればいいの?」Q&A
米ぬかの力、そしてぬか漬けの魅力を紹介してきましたが、では、実際にぬか漬け作りをスタートすると「どうしたらいいの?」と悩む事態に陥ることもあるかもしれません。この項目では、自宅で漬けると直面しがちな疑問をピックアップしQ&Aで紹介します。
【Q1】ぬか漬けにプラスチックの容器を使っているけれど、ホウロウ容器や陶器を使うべき?
【A】 容器への臭い移りを避けて長期的に使え、安定感があってかき混ぜやすいのは、ホウロウ製や陶器ですが、プラスチックの食品用タッパーで容器でも十分です。1人、2人なら2~3L、3、4人なら4Lを目安に選びましょう。深さがある方がかき混ぜやすくなりますが、冷蔵庫に入ることも考慮ポイントです。
【Q2】1つの容器にいろいろな野菜を漬けてもいいの?

【A】 どのような食材を入れても菌が発酵を進めて、ぬか漬けにしてくれます。何種類かを一緒に漬けてもまったく問題ありません。ただし、切り方や大きさが違うと漬かり具合には差は出ます。
【Q3】楽しくて、あれもこれも漬けてみたい衝動に…。ぬか漬けに向いていない食材は?
【A】 定番野菜の他にミニトマト、アボカド、ラディッシュ、オクラ、カボチャ、コリンキー、ジャガイモ、ゆで卵、こんにゃく、豆腐、チーズ、なんでも美味しく漬かります。ただし、匂いが強い食材(タマネギ、ニラ、ニンニクなど)はぬか床に匂いが移ります。別の容器で単品で漬けましょう。肉や魚などの生ものも漬けることはできますが、衛生管理が難しいので、別の容器に漬けて、漬けた後のぬかは捨てるのが安心です。
【Q4】ぬかを洗い流したら、栄養素が減りそう。洗わず、そのまま食べてもOK?
【A】 ぬかを洗い流しても栄養が失われることはほとんどありません。洗わずに食べることもできますが、塩分濃度の高さからも洗ってから食べた方が無難です。
【Q5】ぬか床から浮いてくる水分にも栄養素が溶けている?
【A】 野菜を漬けると野菜の水分が浸透圧で外へ溢れるため、ぬか床の水分量は必然的に上がります。水分量が多いと発酵しやすい環境になりますが、反面、腐りやすくなります。水分の中に栄養素や旨味が入っているのは事実ですが、自宅では腐敗菌を発生させないことが優先順位です。
ぬか床の適切な水分量は55%〜65%とされています。べちゃべちゃではなくふかふか。水分が出たときは、キッチンペーパーをぬか床の上に敷き、余分な水分を吸収させましょう。漬ける前に水洗いした野菜の水分をきちんとふき取ることも忘れずに。
【Q6】ぬか床の水抜きを繰り返すと、旨みが落ちる気がするのですが…?
【A】 できるだけ水抜きはしたくないという場合は、足しぬかを入れて硬さを調整します。目安は米ぬか1カップに対して塩小さじ1杯。大量に入れると乳酸菌とのバランスが崩れるので少しずつ足します。
乾燥昆布はぬか床の水抜きに一役買ってくれます。水分を昆布が吸収してくれるからです。昆布にはグルタミン酸が含まれているので、旨味UPも期待できます。取り出した昆布はもちろん食べられますので、美味しく頂きましょう。
【Q7】美味しくて、つい食べ過ぎてしまう。大丈夫?

【A】 ぬか漬けは塩分を多く含みます。栄養価が高くても食べる量には気をつける必要があります。日本人の食事摂取基準(2020年版)によると一日の食塩相当量の目標量は、男性7.5g未満、女性6.5g未満。ぬか漬けの食べ過ぎはあっという間に目標量を超えてしまいます。定番野菜の漬物の塩分量もぜひ参考に。
【ぬか漬けに含まれる塩分】
・キュウリ(3切15g)・・・0.8g
・ダイコン(3切30g)・・・1.1g
・ナス(3切15g)・・・・・0.4g
【Q8】やらねばならない“かき混ぜ”がストレスに…。
【A】 ぬか床の菌のバランスを保つには“かき混ぜ”というお世話が必要です。冬は一日1回、夏は2~3回、決まった時間に混ぜるのが理想ですが、塩分濃度が適切なら常温で2~3日、冷蔵庫で4~5日の放置は問題ありません。常に冷蔵庫保存なら、一週間に1~2回でも大丈夫なことがほとんどです。混ぜる時は空気を入れながら表面と底のぬかを総入れ替え。指先でちょちょっとかき混ぜたくらいでは乳酸菌が死んでしまいます。
【Q9】まるでペット。旅先でもぬか床が心配で…。
【A】 長期不在の場合は、食材を抜いてぬか床だけの状態にします。一週間以内なら容器のまま冷蔵庫で保存。菌の活動が鈍るため、かき混ぜる頻度を減らせます。一週間以上の場合はチャック付きの冷凍用保存袋に移し替えて冷凍庫で休眠させましょう。自然解凍で再利用が可能です。
“ぬか漬けライフ”でキレイに!
いかがでしたか?すでにぬか床が自宅にある方はさらにモチベーションUPに、まだぬか漬け生活を始められていない方は、さっそくスタートしたいと思われていることでしょう。特に肌のコンディションにも深く関わる腸内環境。乳酸菌は腸に永住することがないため、ぬか漬けで日々の“追い菌”をすることが大切です。まず初めは、市販のぬか漬けからでもOK。ぬか漬けに対して欲が出てきたら、いろいろとこだわってみるのも楽しいものです。新米のぬかは色も美しく、香りも豊か。ぜひ、美しくすこやかな“ぬか漬けライフ”を満喫しましょう。